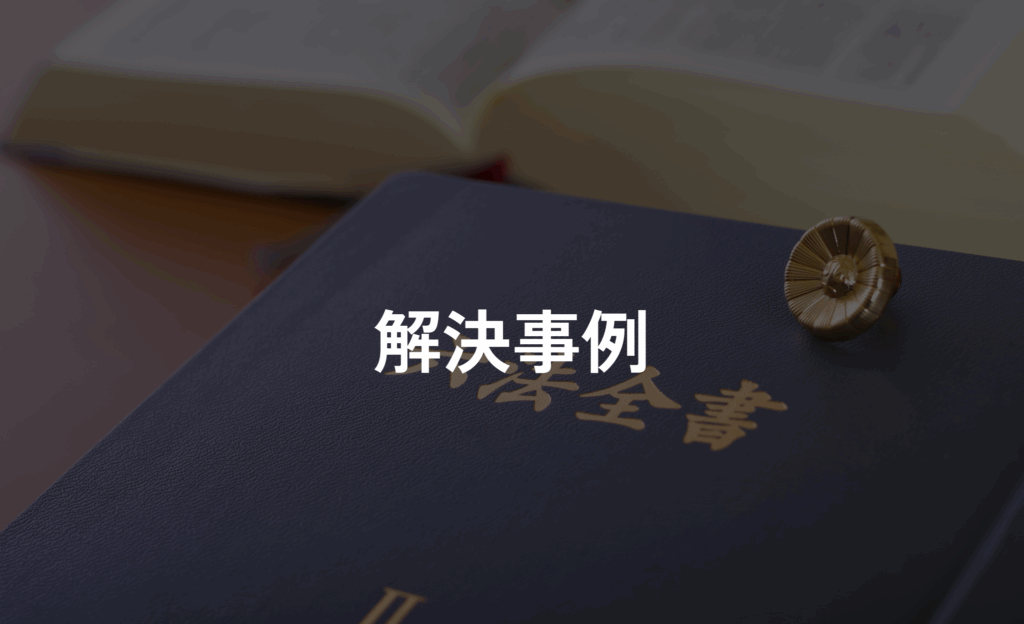
不公平な遺言内容に対し、請求が認められ500万円を獲得したケース
【依頼前の状況】
ご相談者様の父親が亡くなられましたが、遺言書には「全ての財産を長男へ譲る」と記されていました。ご自身の遺留分を求めても、兄が話し合いに応じない状況で、当事務所へお越しになりました。
【依頼内容】
父の遺言により、全ての財産が長男へ渡ることになり、ご自身の取り分が全くない状態になってしまい、兄も応じないため何らかの解決策はないかとご相談をいただきました。
【対応と結果】
まず、兄に対して遺留分侵害額の請求と、相続財産の開示を要求しました。しかし、相手方が応じなかったため、家庭裁判所に調停を申し立てました。調停手続きの中で財産内容が明らかになり、こちらの主張が全面的に認められた結果、ご依頼者様は遺留分として500万円を受け取ることができました。
【弁護士コメント】
遺留分を請求できる権利は、相続の開始などを知った時から1年という期間の定めがあります。心当たりのある方は、お早めにご相談ください。
遺産分割によって代償金1000万円を獲得たケース
【依頼前の状況】
母が亡くなり、子ども3人が遺産を相続しました。しかし、主な財産は実家の不動産(土地と建物)のみという状況でした。
【依頼内容】
相続人の1人が実家に居住していたため、そのまま不動産(土地と建物)を相続したいと希望していました。一方で、ご依頼者様は不動産を売却して金銭の受け取りを希望しており、当事者間で意見が食い違っておりました。
【対応と結果】
遺産分割調停により、不動産を取得する相続人が他の相続人へ金銭を支払う「代償分割」という解決策を提示しました。不動産の価値を査定し、算出された評価額を基に協議した結果、ご依頼者様は代償金として1000万円を獲得することができました。
【弁護士コメント】
代償分割には条件がありますので、一度ご相談ください。
1000万円の借金を相続放棄の手続きで回避できたケース
【依頼前の状況】
事業を経営されていた父が亡くなりました。調査したところ、事業のために1000万円を借り入れており、その負債が残されたままであることが判明しました。
【依頼内容】
手元に残されたプラスの財産は少額の預貯金のみで、多額の借金を返済していく経済的な余裕がないため、どう対応すべきか途方に暮れている、というお話でした。
【対応と結果】
ご依頼を受け、速やかに家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しました。無事に申述が受理された結果、父が残した1000万円の借金を含む一切の債務について、法的に支払う義務がなくなりました。
【弁護士コメント】
相続放棄の手続きは、原則として「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。期限を過ぎると負債も相続することになるため、注意が必要です。
奥様へ多くの財産をのこす遺言を作成したケース
【依頼前の状況】
妻と子供が2人いるが、長年連れ添った奥様へ最大限財産を残したいというご意向をお持ちでした。
【依頼内容】
お子様への遺留分へも一定の配慮をしたうえで、奥様も子供も納得のできる内容の遺言を作成したいというご依頼をいただきました。
【対応と結果】
お子様2人の遺留分(法律で保障された最低限の取り分)を侵害しない範囲で、奥様に多くの財産が渡るような公正証書遺言として作成するサポートをいたしました。また、ご家族への感謝の気持ちを伝える付言事項も盛り込みました。
【弁護士コメント】
遺言書がない場合、ご自身の意思とは異なる相続結果になったりする相続争い(いわゆる「争続」)に発展したりするケースも少なくありません。元気なうちにご自身の意思を形にしておくことを強く推奨します。
将来の認知症に備え、ご自身の意思で後見人を選ぶ任意後見契約を結んだケース
【依頼前の状況】
ご自身の判断能力はしっかりしているものの、将来もし認知症などになった場合、財産管理や身上監護について不安があるため、事前の対策を希望されていました。
【依頼内容】
将来、ご自身の判断能力が低下した際に、ご家族に迷惑をかけないように対策をしておきたい、とご相談をいただきました。
【対応と結果】
ご依頼者様のご意向を丁寧にヒアリングし、①遺言、②財産管理、③任意後見、の3つを組み合わせたプランをご提案。契約内容を公正証書として作成し、法的な効力を確実なものにしました。これにより、生前の財産管理から亡くなった後の手続きまで、すべてを任せられるようになりました。
【弁護士コメント】
元気なうちから将来に備えておくことが何より大切です。弁護士と各種委任契約を結んでおくことで、判断能力が低下しても、亡くなった後も、ご自身の意思に沿った対応が可能になります。また、おひとり様の場合は上記の①~③に加えて、亡くなられた後の関係者への連絡、役所への届け出をはじめとした死後事務もご対応しております。
